オペラント労働・経営総合事務所は、同一労働同一賃金や人事評価制度、働き方改革などを専門とするコンサルタントです。
?090-9688-6271
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそなビル5階
長時間労働の解消に向けてSERVICE&PRODUCTS
長時間労働等による過重労働対策はなぜ必要か
長時間労働等の原因によって、過労による精神疾患の増加、過労死・過労死自殺など大変な社会問題となっています。企業も社会的責任として最重要課題として改善が求められています。
実は長時間労働は企業にとっても大変なリスクがあります。企業には従業員に対して安全配慮義務があります。従業員が長時間労働や仕事の過重によってストレスを受け、過労死や過労死自殺の原因ともなればその家族から多額の損害賠償等を請求される可能性があります。また会社のコスト面を考えた場合、長時間労働などによる過重労働はむしろ生産性を低下させ、仕事に対する創造力や改善力も失わせる結果となります。従業員の創造力や改善力は高付加価値を産みだす源泉です。
実は長時間労働は企業にとっても大変なリスクがあります。企業には従業員に対して安全配慮義務があります。従業員が長時間労働や仕事の過重によってストレスを受け、過労死や過労死自殺の原因ともなればその家族から多額の損害賠償等を請求される可能性があります。また会社のコスト面を考えた場合、長時間労働などによる過重労働はむしろ生産性を低下させ、仕事に対する創造力や改善力も失わせる結果となります。従業員の創造力や改善力は高付加価値を産みだす源泉です。
休日・時間外など長時間労働の削減は業務改善から
長時間労働等の原因による過重労働を改善するには業務改善が不可欠です。
業務改善を行なうためには企業組織における日々の“仕事の流れ”と”資金の流れ(注1)”を把握し、そこに潜むボトルネック(スムーズな流れの障害となっている原因)を捉えることがポイントとなります。
注1)ここでいう「資金の流れ」とは現実の資金(お金)だけではなく、仕事の流れにともなって発生するロス
コストも含めれています。ロスコストはそこでは気が付かなくても、やがてはボディブローのように徐々に
資金を食いつぶし、資金の流れの障害(ボトルネック)になるという主旨です。
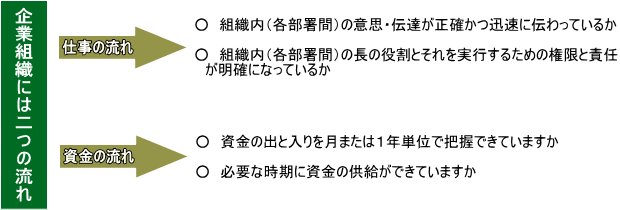
“仕事の流れ”で発生するボトルネックは従業員個人の能力よりも組織におけるロスが大きいと言われています。
特に上記の図で示した二つの項目が事業目的に沿って適切に行なわれているかです。ここがネックになっていると従業員に対
して無駄な労働時間や過重なストレスを発生させます。
まずは、少なくとも以下の内容について点検が必要です。
① 現行の組織図が事業目的に見合う指揮・命令系統や責任と権限が明確になっているか。
② 作業手順や業務マニュアルなども日々の仕事に支障のないように必要に応じて変更されているか。また必要以上に詳細に記
述されていないか(あまり細かく記述されている場合は活用されることは少ない)。
③ 仕事における組織内のトラブルまたはユーザー等からの苦情などを記録に残し、その中身を①と②と照らして、問題ないか
を検討しているか。
④ 従業員の働きやすい職場環境として、無理のない勤務体制づくりに心がけているか。
言い換えれば、常に全力疾走になるような勤務体制になっていないか。
( 「腹八分目に医者いらず」という諺があ るように、いつも満腹の状態では不健康となり、やがては医者の世話になる
という意味もある)。
業務改善を行なうためには企業組織における日々の“仕事の流れ”と”資金の流れ(注1)”を把握し、そこに潜むボトルネック(スムーズな流れの障害となっている原因)を捉えることがポイントとなります。
注1)ここでいう「資金の流れ」とは現実の資金(お金)だけではなく、仕事の流れにともなって発生するロス
コストも含めれています。ロスコストはそこでは気が付かなくても、やがてはボディブローのように徐々に
資金を食いつぶし、資金の流れの障害(ボトルネック)になるという主旨です。
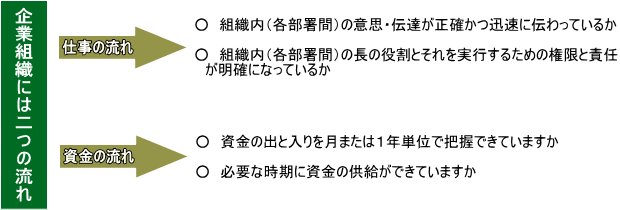
“仕事の流れ”で発生するボトルネックは従業員個人の能力よりも組織におけるロスが大きいと言われています。
特に上記の図で示した二つの項目が事業目的に沿って適切に行なわれているかです。ここがネックになっていると従業員に対
して無駄な労働時間や過重なストレスを発生させます。
まずは、少なくとも以下の内容について点検が必要です。
① 現行の組織図が事業目的に見合う指揮・命令系統や責任と権限が明確になっているか。
② 作業手順や業務マニュアルなども日々の仕事に支障のないように必要に応じて変更されているか。また必要以上に詳細に記
述されていないか(あまり細かく記述されている場合は活用されることは少ない)。
③ 仕事における組織内のトラブルまたはユーザー等からの苦情などを記録に残し、その中身を①と②と照らして、問題ないか
を検討しているか。
④ 従業員の働きやすい職場環境として、無理のない勤務体制づくりに心がけているか。
言い換えれば、常に全力疾走になるような勤務体制になっていないか。
( 「腹八分目に医者いらず」という諺があ るように、いつも満腹の状態では不健康となり、やがては医者の世話になる
という意味もある)。
日々の仕事の流れに生ずるボトルネックの原因を突止めよう
日々の仕事で起きるミス・トラブルやお客からの苦情は必ず仕事の流れに障害となっている原因(ボトルネック)は必ず存在します。それが個人の不注意で生ずるものであっても、個人の問題とせずに組織の問題と捉えることが必要です。そのためにはミス・トラブルやお客からの苦情は必ず記録し、原則として全従業員で共有するようにしましょう。長時間労働等の原因による過重労働を改善するには業務改善が不可欠です。
ミス・トラブルやお客からの苦情については当該所属長が記載して報告書を作成して提出するようにします。
報告書の名称は、「事故報告書」または「ミス・トラブル・苦情等の報告書」とし、当事者からヒアリングをしながら「事実関係を記載する事項」と「それに至った私が考える原因に関する事項」とし、この報告書には対策まで記載は必要ありません。事実関係を記載するときは、原則として5W1H方式が解りやすいと思います。
このように繰り返し重ねることで本質的なボトルネックを発見して、問題解決につながります。
無駄な労働時間の浪費は従業員に目に見えないストレスを与え、企業には資金の意味のない資金の流失をともないます。まずはここから始めるこが長時間労働や過重労働の解消の第一歩となります。
ミス・トラブルやお客からの苦情については当該所属長が記載して報告書を作成して提出するようにします。
報告書の名称は、「事故報告書」または「ミス・トラブル・苦情等の報告書」とし、当事者からヒアリングをしながら「事実関係を記載する事項」と「それに至った私が考える原因に関する事項」とし、この報告書には対策まで記載は必要ありません。事実関係を記載するときは、原則として5W1H方式が解りやすいと思います。
このように繰り返し重ねることで本質的なボトルネックを発見して、問題解決につながります。
無駄な労働時間の浪費は従業員に目に見えないストレスを与え、企業には資金の意味のない資金の流失をともないます。まずはここから始めるこが長時間労働や過重労働の解消の第一歩となります。
休日・時間外等の削減の取組には一工夫
最近、時間外労働を削減するために、"ノー残業デー”を実施している企業が増えているようです。"ノー残業デー”を実施することで、時間内に終わらせるために仕事の工夫も産まれます。それを更に効果を高めるために、このような工夫をしてみてはいかがでしょうか。すなわち効果の"見える化”です。
定額残業代制を実施していた会社で行なった事例です。
"ノー残業デー”を実施した日、またはその期間に電気の消費量を調べたことがあります。やり方は簡単です。
メーターの調べる時間を一定にして、"ノー残業デー”の日とそうでない日をしらべ、模造紙などでみんなが見えるようにする(例えば朝礼やタイムカードの設置場所などに掲示する)。効果が期待できます。
(この会社では、実施半年後に定額残業代制は廃止し、経費の削減の一部を基本給に組み込みました。)
定額残業代制を実施していた会社で行なった事例です。
"ノー残業デー”を実施した日、またはその期間に電気の消費量を調べたことがあります。やり方は簡単です。
メーターの調べる時間を一定にして、"ノー残業デー”の日とそうでない日をしらべ、模造紙などでみんなが見えるようにする(例えば朝礼やタイムカードの設置場所などに掲示する)。効果が期待できます。
(この会社では、実施半年後に定額残業代制は廃止し、経費の削減の一部を基本給に組み込みました。)

